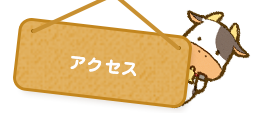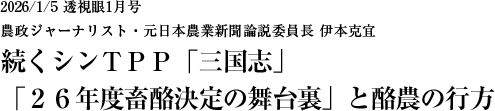
2026年の新しい年が明けた。十干十二支では60年に一度の「丙午(ひのえうま)」。「昭和100年」とも重なる。今年はどんな年になるのか。世界は米国の中間選挙を軸に、日本も総選挙含みの「政治の季節」を迎える。こうした中で「令和のコメ騒動」を引きずりながら、食料安全保障に向けた農政論議が活発化するだろう。あわせて、2026年度畜酪政策価格決定の「舞台裏」を読み解く。

写真=2026年度畜酪政策価格は政治的配慮を踏まえ決定された(畜酪決着内容を報告する2025年12月19日の自民党農林合同会議。正面右側は長井俊彦畜産局長ら農水省幹部)
「丙午」歴史的な転換点
午年(うまどし)は、駆け上がる馬のイメージから「前進」「飛躍」「行動力」など前向きの言葉を連想する。一方で実際の「午年」は歴史的な大事件、転換点となる時期とも重なる。
◇「午年」の主な出来事
・1582年→「本能寺の変」天下統一を目前に織田信長討たれる
・1702年→「赤穂浪士の討ち入り」
・1894年(明治27)→日清戦争勃発
・1918年(大正7)→第1次世界大戦終了、「大正コメ騒動」で内閣倒れる
・1930年(昭和5)→1929年の世界恐慌の余波で昭和恐慌。米価暴落、失業、東北での身売り相次ぐ
・1966年(昭和41)60年前の「丙午」→日本人口1億円に突破。年末12月27日に「黒い霧解散」衆院総選挙、年明け1月8日投開票の結果で自民善戦して安定多数確保、「第2次佐藤栄作政権」
・1990年(平成2)→イラクのクウェート侵攻引き金に湾岸戦争。日本バブル崩壊始まる
・2014年(平成26)→ロシア、ウクライナに侵攻してクリミア併合
・1582年→「本能寺の変」天下統一を目前に織田信長討たれる
・1702年→「赤穂浪士の討ち入り」
・1894年(明治27)→日清戦争勃発
・1918年(大正7)→第1次世界大戦終了、「大正コメ騒動」で内閣倒れる
・1930年(昭和5)→1929年の世界恐慌の余波で昭和恐慌。米価暴落、失業、東北での身売り相次ぐ
・1966年(昭和41)60年前の「丙午」→日本人口1億円に突破。年末12月27日に「黒い霧解散」衆院総選挙、年明け1月8日投開票の結果で自民善戦して安定多数確保、「第2次佐藤栄作政権」
・1990年(平成2)→イラクのクウェート侵攻引き金に湾岸戦争。日本バブル崩壊始まる
・2014年(平成26)→ロシア、ウクライナに侵攻してクリミア併合
このように歴史的な大事件も多い。キーワードは「戦争」「政治」か。過去を振り返り今年を展望すると、「政治」では11月3日の米国上下院の中間選挙、日本では10月下旬に衆院任期が2年を切ることから高市政権下で3月末の新年度予算可決以降、6月下旬の通常国会会期末、10月21日の高市政権発足1年あたりを一つの節目に解散・総選挙の動きが表面化する可能性が高い。
シンTPP三極構図「トランプ・プーチン・北京」
世界は「新三国志」とも呼ぶべき三極構図で動く。今年はその傾向が一段と強まるのは間違いない。この構図を筆者は別名「シンTPP」と名付けた。3人の主役であるトランプ・プーチン・北京(習近平)の頭文字をとった。
本来の通商交渉TPPも原則「ゼロ関税」とした“異常協定“だったが、「シンTPP」もとんでもない3人組による国際的な枠組みだ。この構図は3つの安全保障である「軍事」「エネルギー・資源」「食料」を激しく揺さぶり続ける。当然、酪農分野でも輸入飼料の不安定化など影響が懸念される。
2026年度畜酪決着の舞台裏
ここで、2025年12月下旬に決定した2026年度畜酪政策価格・関連政策の舞台裏を探りながら、今年の畜酪問題の行方を考えよう。
政府・自民党の2026年度畜産・酪農政策価格・関連対策は12月19日実質決着、翌週22日の農水省の食料・農業・農村政策審議会畜産部会で正式に決定した。焦点の加工原料乳補給金等はキロ12円の大台に乗った。肉用牛子牛保証価格も軒並み引き上げた。今回は新酪農・肉用牛近代化基本方針(酪肉近)初年度に当たり全畜種で政治的な配慮がなされたと言っていい。
鉄壁〈森山―江藤ライン〉と関係者「大台に乗った」
26年度畜酪政策価格は、農業団体の要望を踏まえた自民党農林議員の主導で決まった。決着した19日の自民農林合同会議の開催設定時間は午前11時。通常昼前に設定る場合は、前日には決定内容が固まったか、あるいは財政当局との折衝難航が予想されるため、一応経過報告をして、その後夕方に再度、合同会議を開き最終的な決着内容を報告することが多い。
今回は昼前に会議で決着内容とともに、畜酪諸課題をめぐり詳細に目配りした14項目にも及ぶ決議文が出た。その意味では、高市内閣の積極財政、食料安保への理解もあり、政府・自民党の折衝が円滑に進んだと言えよう。加工原料乳総交付対象数量の内容なども、事務レベルの創意工夫の跡が読み取れる内容だ。
政策価格は、当然算定ルールに沿うが、直近の物価修正などで調整を加え、さらに関連対策で上乗せして政治的配慮にも応じる手法を取る。今回も同様だ。特に関係者で「大台に乗った」とされたのが加工原料乳補給金等のキロ当たり12円突破、総交付金対象数量350万トン、さらに肉用子牛の主力・黒毛和種の1頭当たり保証基準価格が60万円の大台にのったことだ。保証基準価格は、子牛の市場平均価格が保証基準価格を下回った際に差額を補てんする仕組みで、いわばセーフティーネットとなる。保証基準価格を上げることは、それだけ子牛生産者の経営支援につながる。
水面下で調整が進められた肉牛関連は、最終的にさまざまな政策的配慮がなされた。共に農相経験者で主産地・南九州選出の二人の自民農林のドン、森山裕、江藤拓両氏の圧倒的な政治力が形となって現れた。
政策決定の内容は以下の通り。
〇26年度畜酪対策の主な内容
◇酪農生産者補給金等関連
・加工原料乳補給金9円11銭→2銭上げ
・集送乳調整金2円83銭→10銭上げ
・alic加算 9銭→1銭上げ
・補給金等合計12円3銭→13銭上げ
・総交付対象数量325万トン→据え置き
・alic事業 25万トン→7万トン増
・合計 350万トン→7万トン増
◇肉用子牛生産者補給金(保証基準価格)
・黒毛和種60万円→2.6万円上げ
・褐毛和種54.7万円→2.4万円上げ
・その他肉専34.8万円→1.4万円上げ
・乳用種17.4万円→1万円上げ
・交雑種27.4万円→据え置き
(※→は前年度対比。加工原料乳補給金等はキロ、総交付数量alic事業25万トンのうち20万トンの単価は脂肪分のみで半額。子牛補給金は1頭当たり)
〇26年度畜酪対策の主な内容
◇酪農生産者補給金等関連
・加工原料乳補給金9円11銭→2銭上げ
・集送乳調整金2円83銭→10銭上げ
・alic加算 9銭→1銭上げ
・補給金等合計12円3銭→13銭上げ
・総交付対象数量325万トン→据え置き
・alic事業 25万トン→7万トン増
・合計 350万トン→7万トン増
◇肉用子牛生産者補給金(保証基準価格)
・黒毛和種60万円→2.6万円上げ
・褐毛和種54.7万円→2.4万円上げ
・その他肉専34.8万円→1.4万円上げ
・乳用種17.4万円→1万円上げ
・交雑種27.4万円→据え置き
(※→は前年度対比。加工原料乳補給金等はキロ、総交付数量alic事業25万トンのうち20万トンの単価は脂肪分のみで半額。子牛補給金は1頭当たり)
「進次郎農水幹部人事」の余波
今回の畜酪決着を別の角度から見よう。例年、畜酪決定は政治家、関係団体の多さから農畜産物政策論議の中でも政治的な色彩が強い。小泉進次郎前農相による7月の農水省幹部人事も微妙に影響したと見る向きもある。
畜酪論議で特に難所は、直接、生産者の手取り所得となる補給金単価など酪農関連だ。専業農家が大半で、北海道の最大品目、中央畜産会、中央酪農会議、酪農政治連盟をはじめ政治力を持つ関係団体も多い。対応した農水省は長井俊彦畜産局長、関村静雄審議官、須永新平牛乳乳製品課長ら。
長井氏は、渡辺毅農水次官の留任を決めた小泉人事に伴い次官候補の官房長ポストから外され、経験のない畜産局長となった。自民党は鋭い問題意識を持つ簗和生畜酪委員長がひかえる。畜酪決定で失敗すれば「調整能力がない」と長井局長の評価が下がるのは間違いない。
一方で、須永課長は自ら主産地・北海道に何度か出向き関係者の意見を聞くなど、環境整備を精力的にこなしてきた。牛乳乳製品課長ポストは、かつて「3白」といわれる白物の米、牛乳、砂糖の一角で、関係者との難しい政治調整が問われる。キャリア官僚が「次」にステップアップする登竜門でもある。実際に次官や長官となった官僚も複数いる。こうした中で、全体調整は関村審議官が担ったといえ、それぞれ「次」をにらんだ長井局長、須永課長が、懸命に自民農林幹部の要求に応えた「結果」とも言える。
高市政権初の政策決定の意義
26年度畜酪政策価格は、経済安全保障の一環である食料安全保障を全面に掲げる高市早苗内閣の実質的に初の政策決定となるだけに、決定内容が注目された。
決定内容は、農畜産業振興機構(alic)事業による緊急措置も加え畜酪農家にとって政治的配慮の行き届いた決着となった。「高市農政」の行方を占う。公明党に代わり連立政権を組んだ合理化農政を目指す日本維新の会の影響も懸念されたが、「閣外協力」ということもあり自民党主導での政策決定となったと見ていい。
一方で、「高市官邸」は安倍晋三元首相のカラーも一段と染まりつつある。内閣広報官に安倍氏の秘書官でスピーチライターだった経済産業省官僚・佐伯耕三氏が就く。既に安倍内閣時に辣腕を振るった同省出身の今井尚哉氏も内閣官房参与にいる。10年前の理不尽な「官邸農政」も念頭に置く必要がある。
残された宿題「畜安法改正」「生乳需給」「飼料自給」
多くの政治的配慮がなされた今回の26年度畜酪政策価格・関連対策だが、やはり大きな「宿題」も残った。
喫緊の課題は年末の生乳廃棄回避の需要拡大と完全処理の「需給」対応。年明け1月からはJA全農の配合飼料供給価格が全畜種平均で前期(25年10~12月)に比べトン当たり4200円上がる。飼料コストは畜酪経営経費の約半分を占める。国産飼料の自給率をどう高めるか。農水省は良質粗飼料向けに青刈りトウモロコシ増産を強調するが、肝心の濃厚飼料代替の子実用トウモロコシなどを計画的に増やしていかなければ、過度の輸入飼料依存による加工型畜酪からいつまでも脱しきれない。
そして改正畜安法の課題だ。2025年12月18日の衆参農水委員会でも立憲民主党・徳永エリ参議員(北海道)からも指摘があった生乳需給対応と改正畜安法の関係だ。
もともと生乳流通自由化に伴い指定団体の需給調整機能弱体化を招く“欠陥法“との指摘が強い。農水省は生乳需給安定へ規律強化にとどまらず、クロスコンプライアンスを加工原料乳補給金そのものへの適応のため法改正の検討を早急に進める大きな「宿題」が残った。
(次回「透視眼」は2026年2月号)
(次回「透視眼」は2026年2月号)
- 2026年 1月号
- 2025年 12月号
- 2025年 10月号
- 2025年 8月号
- 2025年 6月号
- 2025年 4月号
- 2025年 2月号
- 2025年 1月号
- 2024年 10月号
- 2024年 9月号
- 2024年 8月号
- 2024年 6月号
- 2024年 4月号
- 2024年 2月号
- 2024年 1月号
- 2023年 12月号
- 2023年 10月号
- 2023年 8月号
- 2023年 6月号
- 2023年 4月号
- 2023年 2月号
- 2023年 1月号
- 2022年 12月号
- 2022年 10月号
- 2022年 8月号
- 2022年 6月号
- 2022年 4月号
- 2022年 2月号
- 2022年 1月号
- 2021年 12月号
- 2021年 10月号
- 2021年 8月号
- 2021年 6月号
- 2021年 4月号
- 2021年 2月号
- 2021年 1月号
- 2020年 12月号
- 2020年 10月号
- 2020年 8月号
- 2020年 6月号
- 2020年 4月号
- 2020年 2月号
- 2020年 1月号
- 2019年 12月号
- 2019年 10月号
- 2019年 8月号
- 2019年 6月号
- 2019年 4月号
- 2019年 2月号
- 2019年 1月号
- 2018年 12月号
- 2018年 10月号
- 2018年 8月号
- 2018年 6月号
- 2018年 4月号
- 2018年 2月号
- 2018年 1月号
- 2017年 12月号
- 2017年 10月号
- 2017年 8月号
- 2017年 6月号
- 2017年 4月号
- 2017年 2月号
- 2017年 1月号
- 2016年 12月号
- 2016年 10月号
- 2016年 8月号
- 2016年 6月号
- 2016年 4月号
- 2016年 2月号
- 2016年 1月号