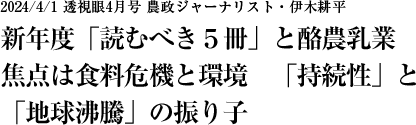

写真=農政関連本や官邸農政と酪農改革など読むべき本は出版されている(農水省地階の三省堂書店農水省売店で)
2024年度は世界新秩序の揺籃期かもしれない。歴史の〈振り子〉は地球沸騰を前に「変化」と「持続性」の間を右に左にと揺れる。そんな中で、酪農乳業はどうあるべきか。キーワードは社会的共通資本を表す〈コモンズ〉。今年度に読むべき5冊プラスαで、今後の針路のヒントを探ろう。具体的には①『食料危機の未来年表』②『「豊かさ」の農本主義』③『日本人は「食なき国」』を望むのか』④『マルクス解体』⑤『レジリエンスの時代』――だ。
A・R・E(アレ)=環境重視の持続可能な農業・酪農
「読むべき5冊」をやや先取りし、今年度の農業と酪農乳業の行方と絡めれば、連覇がかかる阪神タイガース・岡田彰布監督のメタファー(隠喩)であるA・R・E(アレ)に行き着くのではないかとも思う。この言葉は2023年流行語大賞にも輝いた。
A・R・Eを英語の頭文字と考えたい。Aはアグリ(農業)、Rはレジリエンス(強靭性)、Eはエンバイロメント(環境)。レジリエンスは災害時などに使われる立ち直る強靭性。つまりは持続可能性と言い換えてもいいだろう。「読むべき5冊」の最後、話題の書『レジリエンスの時代』とも関連する。
ロシアが引き金を引き気候変動が増幅する食料危機、環境調和型の「みどり戦略」も含め、今後の農業、酪農乳業はA・R・Eの英頭文字への対応が一段と重要となる。基本法見直し法案、食料有事への新法も今国会中に成立する。「読むべき5冊」はA・R・E=環境重視の持続可能な農業・酪農乳業を考える航路への水先案内人、ガイドの役目も果たすだろう。
1冊目『食料危機の未来年表』(高橋五郎、朝日新書) キーワード本当の日本の自給率は18%、世界128位という実態
ウクライナ問題は、あらためて食料が「武器」となることを示した。地球温暖化に伴う気象危機は食料危機とも連動する。国会では食料安全保障強化への論議が進む。
そこで24年度必読の一冊目として『食料危機の未来年表』を挙げよう。筆者・高橋五郎氏は中国農業の専門家で、国際的視点で食料・農業問題を読み解く。一方で日本の農政には精通していない点は留意が必要だ。それでも、ユニークな視点で〈未来年表〉を明らかにしており参考になる。
そこで24年度必読の一冊目として『食料危機の未来年表』を挙げよう。筆者・高橋五郎氏は中国農業の専門家で、国際的視点で食料・農業問題を読み解く。一方で日本の農政には精通していない点は留意が必要だ。それでも、ユニークな視点で〈未来年表〉を明らかにしており参考になる。
まず「隠れ飢餓」という造語で日本の実態を表す。一見飽食のようだが、大部分の食料を輸入しなければ一日も成り立たない。次に世界初という182カ国の食料自給率試算を公表。日本はカロリーベース自給率(全穀物・全畜産物)で18%、世界128位、たんぱく質自給率(50品目)で27・1%、155位。「日本の食料問題の実態は農業外問題、外交問題であり政治の問題」「その根幹は日本の対米従属関係に由来」は傾聴に値する。
打開策として市民・農家株式契約システムの導入を挙げた。自由貿易で食料問題は解決しない、規模拡大路線では行き詰るとして、日本の農家の適正規模は10~20ヘクタール程度、理想は地域循環のデンマーク農業とする。
プラスα本として、『日本は食料危機にどう備えるか』(石坂匡身他、農文協)を見よう。副題は「コモンズとしての水田農業の再生」。
基本計画で食料自給率目標を一度も達成されていない。主な原因は農地減少に歯止めがかからない中で、工場式畜産を続けていることにある。「工場式畜産」とは国内の草資源等を活用せず輸入飼料穀物依存の実態を指す。
基本計画で食料自給率目標を一度も達成されていない。主な原因は農地減少に歯止めがかからない中で、工場式畜産を続けていることにある。「工場式畜産」とは国内の草資源等を活用せず輸入飼料穀物依存の実態を指す。
水田農業を日本のコモンズ(社会的共通資本)としてとらえ、異形の工場式畜産を脱し、水田、未利用農地、草地活用の本来的な畜産に戻す。食料安保の「不測」に備える。草地は〈耕地予備軍〉とはっきり位置付ける。
『小麦の地政学』(セバスティアン、原書房)も未来の食料問題でヒントに満ちる。注目すべき一つは温暖化で「シベリアは将来の穀倉」との指摘だ。軍事大国ロシアは気候変動でも〈追い風〉が吹くということか。
『小麦の地政学』(セバスティアン、原書房)も未来の食料問題でヒントに満ちる。注目すべき一つは温暖化で「シベリアは将来の穀倉」との指摘だ。軍事大国ロシアは気候変動でも〈追い風〉が吹くということか。
2冊目『「豊かさ」の農本主義』(大石和男、人文書院) 「農と何か」。環境の衣まとう新しい〈農本主義〉に注目
食料危機が叫ばれ、食料安保が国会論議となる中で、あらためて〈温故知新〉古くて新しい「農本主義」を考えたい。
農本主義なる単語は、よく農業団体の幹部が口にする。「農は国の本なり」、そして、食料安保論議の通常国会でも岸田文雄首相の口からも同様の「農は国の本なり」の言葉が出た。これらはあまり定義がはっきりしない。要するに農業は大切な産業だほどの意味だろうが、四半世紀ぶりの基本法見直しの中でも、政府から先進国最低の食料自給率に落ち込んだ地域農業衰退の反省の弁は一向に聞こえてこない。反省なくして再興なしである。こんな実態の中で農本主義は軽い言葉と見えてしまいかねない。いやそんなことはない。〈真〉の農本主義は国の行く末を決めるやはり大本、大方針のはずだからだ。
先日、農政指針、コメ生産調整などに大きな影響力を持ってきた生源寺真一東大名誉教授(現日本農業研究所研究員)とインタビューを兼ねじっくり話し込んだ。この中で「農本主義が最近再び注目されているがどう思うか」と聞いてみた。同氏は「○○主義」という言葉は排他的になりがちでふさわしくないとしながら、環境、有機農業とも絡み若い研究者が取り上げることはいいことだとして「むしろ〈農本思想〉とよぶべきではないか」と指摘した。傾聴に値する。
本題に戻ろう。新たな視点で農本主義を読み解いた試みの大著『「豊かさ」の農本主義』(大石和男著)は、表題の〈豊かさ〉に今日性を持たせた。史的展開を踏まえながら、現代社会の中で農本主義をどうとらえ、意味づけるのか。重要なのは、「農本思想の戦後史」の中でキーワードに〈農本主義〉とともに〈有機農業〉〈自給〉〈百姓〉さらには〈コミューン〉、農村女性の〈ネットワーク〉を挙げた点だ。経済学者・宇沢弘文氏の「社会的共通資本」にも触れている。元全共闘運動の指導者・藤本敏夫氏の「自給」思想、生産現場に軸足を置いた「減農薬」「生態系」などを唱えた宇根豊氏などを新たな農本主義の序列に加えた点は新鮮だ。
農業史の視点で若く新たな研究者として登場した藤原辰史京大准教授の『農の原理の史的研究』も同著で批判的に取り上げた。農本主義者の言動を批判の対象ととらえるのではなく、農本思想から社会変革に向けた創造性をとらえようとする視点こそ重要だと説く。ただ「史的研究」が医・食・心・政・技を統合する未来の農学を目指す〈新たな農学原論〉の試みであることが斬新だ。
第7章「宇根豊による「減農薬」から「農本主義」への思想展開」は、〈新しい農本思想〉への大きな方向性を示す。ここでプラスα本として宇根氏の『農本主義のすすめ』(ちくま新書)を見てみよう。「農は天地に浮かぶ大きな舟」「農本主義とは「農」を農業ではなく、農と見る見方を取り戻すこと」「農は近代化できない、市場経済では評価できない世界がある。そういう世界こそ「農」の本質」と、実践も踏まえ分かりやすく説く。ただ、先の藤原氏は歴史学者の冷徹な眼で〈宇根農本思想〉の不完全さも指摘し、的を射ている。
筆者自身、20年近く前に取材で福岡の宇根氏の自宅を訪ねたことがある。秋、水稲の圃場で収穫間際の写真を撮ると、宇根氏の周りに赤トンボがたくさん寄ってきて驚いた。減農薬の水田は生物多様性の宝庫、田んぼはまさに生き物の〈ゆりかご〉の役目を果たしているのを実感したのを昨日のように思い出す。
3冊目『日本人は「食なき国」を望むのか』(山下惣一、家の光協会) 日本は「小農」=家族農業の国だ。「良か仕事」が未来をつくる
著名な農民作家・山下惣一氏は2022年7月に逝った。享年86。佐賀・唐津に根を張り農業の現場から鋭い農政批判を浴びせてきた論客で知られていた。前述した宇根氏とも〈盟友〉である。
多くの著作があるが、基本法見直しの今、あらためて本人の主要論点でもある『日本人は「食なき国」を望むのか』を再読したい。「透視眼」4月号で挙げた「読むべき5冊」は近著だが、山下氏の同著は10年前、2014年の古い著作である。だが、再読するとちっとも古びていない。むしろ、今の農業・食料危機を言い当てているかのようだ。同氏の死から1年後の2023年9月、NHKが「日本人は農なき国を望むのか~農民作家・山下惣一の生涯」を全国放映し反響を呼んだ。番組タイトルは同著に因む。
「農水省は半世紀以上、大規模化の構造改革を進めてきた。その成果がほかでもない農業・農村の惨状である」「私は家族農業を「小農」、企業農業を「大農」として、経済規模ではなく「目的」で区別してきた。小農の目的は「暮らし」であり、大農は「利潤」だ」「日本は99%小農の国、世界に冠たる家族農業の国だ」「本書は小規模農家に自信と希望、それ以上に消費者のこの国の家族農業への視界と支援を願って書いた」。
山下氏のいう「良か仕事」とは、直接カネにはならないが将来につながる仕事。山の手入れ、田の排水、棚田周りの草取りなど。「百姓仕事でカネにならないものにも価値がある」と強調する。そして末尾「強い農業が生き残るのではない。生き残った農業が強いのだ――楽しくやろうぜ!」で締めくくった。再読の価値ありである。
4冊目『マルクス解体』(斎藤幸平、講談社) 脱成長、環境重視のマルクスを「発見」、今こそ有用な「資本論」の意義説く
斎藤幸平東大准教授は、日本人研究者としておそらく哲学者・浅田彰氏以来のインパクトを国内外に与えている学者だ。一般向けに分かりやすく書いた同氏の『人新世の「資本論」』は「新書大賞2021」1位となった。『マルクス解体』はこの新書をさらに降り下げた最新版だ。2023年2月、英ケンブリッジ大学出版から刊行された日本語版で、つまり逆輸入本である。同著が英語版で世界中に読まれている証しだろう。
気候変動の猛威、世界的格差拡大、「もしトラ」と称される米大統領選でのトランプ氏再登板の動きなど分断社会の今こそマルクスの理論は有効だと説く。ここで肝心なのはマルクス理論とマルクス主義の峻別だ。筆者個人も大学時代に農業経済学を通じマルクス経済学に接し、斎藤幸平氏の読み解くマルクス『資本論』には目からうろこの感慨を持った。著書の表題『マルクス解体』は少し誤解を招く。何もマルクス理論を分解するというのではなく、その本質を最新データ、知見を交えて読み解くという意味合いだ。
〈マルクス主義〉として〈主義・イズム〉の色眼鏡、フィルターがかかった瞬間からマルクス理論は歪曲されて理解、解釈され、各国共産党をはじめとした左翼陣営で浸透、流布された。実はこれらはマルクス主義と言うより、レーニン死後のソ連を引き継いだスターリン色が濃厚なスターリン主義と言い換えてもいいものだ。斎藤氏はその理論的修正とマルクスの今に通じる先見性を見出だした。
左派からポスト資本主義の新たな姿を示した。キーワードは環境重視と脱「成長」。これまでの成長重視のマルクス主義を「プロメテウス派」をした。マルクスの著作にも登場するプロメテウスは、ギリシャ神話で天界の火を盗み人間に与えた神だ。火は人類に技術、経済発展をもたらす一方で戦争など禍ももたらす。
ここで話題を『マルクス解体』と食料・農業問題の関連で見よう。斎藤氏はポスト資本主義を〈脱成長コミュニズム〉と見る。社会経済循環、今の環境重視のサステナブル社会を見通した〈緑のマルクス〉を描く。つまり社会的共通資本である〈コモンの再生〉を目指す。その重要な柱には協同組合が位置づく。
規制緩和を前面に出した新自由主義の基づく「民営化」に抗した、住民による自主的管理の「市民営化」を唱える。食料・農業問題でも協同組合を主体とした競争よりも共創を。脱成長で環境重視の持続可能な農業の確立こそが重要だと説く。「農業の成長産業化」を前面に掲げたアベノミクス官邸農政による、指定団体の生乳一元集荷廃止、改正畜安法施行とは〈真逆〉の発想なのも分かる。
プラスα本として『資本主義の次に来る世界』(ジェイソン・ヒッケル、東洋経済新報社)。「多い方が貧しい。少ない方が豊か」と脱成長を唱え、「本種が語るのは破壊ではない。語りたいのは希望だ」と強調する。
アベノミクス官邸農政の欠陥と酪農改革では『天地の防人 食農大転換と共創社会』(伊本克宜、kkベストブック刊)第6章「官邸農政」と終焉アベノミクスに詳しい。
アベノミクス官邸農政の欠陥と酪農改革では『天地の防人 食農大転換と共創社会』(伊本克宜、kkベストブック刊)第6章「官邸農政」と終焉アベノミクスに詳しい。
5冊目『レジリエンスの時代』(ジェレミー・リフキン、集英社) どうする地球「再野生化」 GDPから共有材重視の指標へ転換
紹介する最後の『レジリエンスの時代』は、一つ前、4冊目の斎藤幸平氏『マルクス解体』と関連する。経済成長、効率化は生体系とインフラを破壊し人類を脅かしている。脱するには「レジリエンスの時代」への大転換が欠かせないと訴える。斎藤氏は〈緑のマルクス〉を発見しマルクス理論に新たな地平を開いた。環境重視、脱成長を説いた『マルクス解体』はレジリエンス時代と共振する考え方だろう。
『レジリエンスの時代』は国際社会がパラダイムシフトを迎える教科書となりえる。序文「ウイルスが次々と現れる。そして地球は刻々と再野生化(リワイルド)している」。キーワードは〈リワイルド〉。新型コロナウイルスは地球全体を揺さぶり、気候変動を人類に牙をむく。年明けの能登半島地震をはじめ、世界各国で続くタイ地震、地球温暖化で猛威を増す巨大な山火事の頻発。自然は人の手に負えない野生化しているという見立てだ。
ではどうする。地球を人類に適応させるのではなく、人類を地球に適応させる。プラネタリーバウンダリー、地球限界と言われる状態から環境負荷を抑えた循環型経済への転換だ。平たく言えば、靴のサイズの足を合わせるのではなく、足に靴を合わせる。当たり前のことが、成長至上主義の膨張経済の中で進み、地球が悲鳴を上げているのだ。
日本の農政でも思い当たる。10年近く前の安倍官邸農政での一連の農政改革、具体的には農協改革、酪農制度改革、さらには全農株式会社化提案など。農業生産現場の実態(足のサイズ)に沿ったのではなく、官邸主導の農業成長産業化、規制緩和を大前提に机上の理論(靴のサイズ)での農政展開は、今も禍根を残している。四半世紀期ぶりの現在の基本法見直しは、かつての官邸農政の悪弊を転換するものでなければならない。『レジリエンスの時代』はその延長線で読み解ける。
経済指標を規模の経済、GDPからQLI、つまり乳児死亡率、共有材基盤(コモン)、空気、水などの状態を組み入れた循環型への改訂を提案する。食料、農業生産との関連で注目したいのが、「健全な土壌は食料生産の基盤」とするFAO(国連食糧農業機関)の考え方を「実に的確」と評価している点だ。健全で健康な土壌、土づくり。農水省「みどり戦略」でも肥料、農薬の生産資材投入の削減、有機農業の拡大で共通する。
ここで循環型経済を農業、酪農に当てはめて考えたい。本来の酪農は人間が消化できない草資源、粗飼料を有効活用し良質な栄養素に変え牛乳・乳製品を安定的に提供する仕組みが基本だった。100年前、雪印メグミルクの創始者・黒沢酉蔵が「健土健民」の4文字で見事に集約した精神だ。地球リワイルド、プラネタリーバウンダリーの現在、酪農生産の本質を突くこの「健土健民」の意味合いが一段と重みを増す。それは「レジリエンスの時代」との共振でもあるはずだ。
プラスα本として、劣化する土壌を直視し解決策を示す米ワシントン大学地形学研究グループ教授・ディビッド・モントゴメリーの一連の本が手助けしてくれる。『土の文明史』『土・牛・微生物』はいずれも築地書館から邦訳されている。土壌劣化と文明衰退の興味深い話を披露するが、ここで彼は土壌劣化を防ぎ地力回復のためには「農場の大小を問わず作物栽培と畜産を再び結合することだ」と唱える。土と牛と微生物の共生こそ地球環境救済の重要な柱だという。先の「健土健民」、さらには脱成長とも結びつく。
『土の文明史』第10章〈経済理論の中の農業〉321ページにある指摘を注視したい。「資本主義もマルクス主義も経済理論は、資源が無尽蔵であるか際限なく代替可能と考えていた」。その証拠にマルクスの盟友・エンゲルスの言葉も引用。「土壌劣化の問題を一言で片づけた。「土地の生産性は、資源、労働力、科学の投入で無限に増大しうる」を挙げた。
これはエンゲルスと著者モントゴメリー双方に誤解がある。モントゴメリーは一般的なマルクス主義経済をとらえている。先の斎藤幸平氏『マルクス解体』で触れたように、マルクス理論で主流の経済拡大、成長主義の「プロメテウス派」の主張で、エンゲルス、さらにはスターリンが理論的土台をつくった。
だが「緑のマルクス」はそうではない。むしろ最晩年のマルクスは循環経済を重視し、その意味ではレジリエンスの時代を見通していた。読むべき5冊目の『レジリエンスの時代』は、そんな思索も巡らせる本だ。
(次回「透視眼」は6月号)
(次回「透視眼」は6月号)
- 2024年 4月号
- 2024年 2月号
- 2024年 1月号
- 2023年 12月号
- 2023年 10月号
- 2023年 8月号
- 2023年 6月号
- 2023年 4月号
- 2023年 2月号
- 2023年 1月号
- 2022年 12月号
- 2022年 10月号
- 2022年 8月号
- 2022年 6月号
- 2022年 4月号
- 2022年 2月号
- 2022年 1月号
- 2021年 12月号
- 2021年 10月号
- 2021年 8月号
- 2021年 6月号
- 2021年 4月号
- 2021年 2月号
- 2021年 1月号
- 2020年 12月号
- 2020年 10月号
- 2020年 8月号
- 2020年 6月号
- 2020年 4月号
- 2020年 2月号
- 2020年 1月号
- 2019年 12月号
- 2019年 10月号
- 2019年 8月号
- 2019年 6月号
- 2019年 4月号
- 2019年 2月号
- 2019年 1月号
- 2018年 12月号
- 2018年 10月号
- 2018年 8月号
- 2018年 6月号
- 2018年 4月号
- 2018年 2月号
- 2018年 1月号
- 2017年 12月号
- 2017年 10月号
- 2017年 8月号
- 2017年 6月号
- 2017年 4月号
- 2017年 2月号
- 2017年 1月号
- 2016年 12月号
- 2016年 10月号
- 2016年 8月号
- 2016年 6月号
- 2016年 4月号
- 2016年 2月号
- 2016年 1月号


